
「ナリタブライアン かわいそう」と検索したあなたは、名馬として名を刻んだその馬の背後にある真実を知りたいと思っているのではないでしょうか。
ナリタブライアンは1994年に三冠馬となり、圧倒的な実力で強すぎると称されましたが、その後の戦績や高松宮記念への出走、そして悲しい死因まで多くの出来事が重なり、今ではかわいそうという印象を持たれることも少なくありません。
その背景には、馬主の判断や、レースローテーション、そして最後に訪れた突然の腸捻転による死が大きく関わっています。
また、子供や産駒としての実績が限られていたことや、子孫に大きな活躍が見られなかったことも、悲運な名馬として語られる理由の一つです。
さらに、ナリタブライアンの兄であるビワハヤヒデとの兄弟関係や、ライバルたちとの名勝負、そしてシャドーロールをつけた姿なども、今なお語り継がれる要素となっています。
かわいいと言われる優しい性格や見た目、ファンとの関わりもまた、彼の死後に多くの人の心を動かしました。
墓に手を合わせるファンや、ウイポなどゲームの中で再びその走りを見たいと願う声も後を絶ちません。
本記事では、戦績や悔し泣きの逸話を含め、なぜ彼がかわいそうと呼ばれるのか、そのすべてを丁寧に紐解いていきます。
なぜ「ナリタブライアンはかわいそう」と言われるのか?悲劇の名馬の真実
- ナリタブライアンの死因とは?屈腱炎から腸捻転による安楽死まで
- 高松宮記念出走は正しかったのか?無理なローテーションの代償
- ナリタブライアンと馬主の関係──金か名誉か、決断の裏側
- 「悔し泣き」の逸話は本当?天皇賞での涙の真相とは
- 晩年の扱いは適切だったのか?ナリタブライアンの戦績から考察
- タテガミのオークション騒動とは?「かわいそう」と言われる理由
死因は?屈腱炎から腸捻転による安楽死まで
ナリタブライアンの死因は腸捻転によるもので、最終的には安楽死の処置が取られました。
これは、ただの病気ではなく、名馬としての栄光の裏に潜んでいた悲劇の最終章といえます。
屈腱炎を患ってからナリタブライアンの体調は不安定になり、最終的に命を奪ったのは激しい腹痛をともなう腸の疾患でした。
馬の腸捻転は、腸がねじれて血流が止まり、急激に状態が悪化するもので、進行が早いため手の施しようがない場合が多いです。
1998年9月27日、栗東トレーニングセンターで異変が確認されました。
すでに胃の破裂と腸捻転が発生しており、獣医師たちが緊急に開腹手術を行おうとしたときには、治療不能と判断され、安楽死という苦渋の決断が下されました。
まだ8歳という若さでした。
これは競走馬としても、種牡馬としてもこれからを期待されていた存在だっただけに、多くの関係者やファンに衝撃を与えました。
また、死後にまつわる話題として、「たてがみを切り取られた」との噂も流れました。
これはバラエティ番組『とんねるずのハンマープライス』で「ナリタブライアンのたてがみ」が出品されたことによるものですが、実際にはたてがみを切られたのではなく、ブラッシングの際に自然に抜け落ちた毛を提供したという経緯があります。
名馬の死としてはあまりにも突然で悲しいものであり、多くの人が「かわいそう」と感じる所以となっています。
高松宮記念出走は正しかったのか?無理なローテーションの代償
ナリタブライアンのキャリア後半において、とくに議論を呼んだのが「高松宮記念」への出走でした。
この判断は果たして正しかったのか、多くのファンや関係者の間で長く語られるテーマとなっています。
本来、ナリタブライアンの適性は中長距離にあり、スプリントG1である高松宮記念(1200m)への出走は異例の選択でした。
出走時はすでに股関節炎からの復帰途上で、全盛期の走りを取り戻せていない状況だったにもかかわらず、短距離戦に出走させられたことで、「無理をさせたのではないか」と批判の声があがりました。
このレースは1996年に行われ、結果は6着という平凡なものに終わっています。
当時のファンの間でも、「本来出すべきではなかった」「クラシック三冠馬が最後に出るレースではない」との意見が多く見られました。また、ある投稿者は「宮記念は走るべきじゃなかったと思った」と述べており、名馬にふさわしくない舞台であったとする意見も強いです。
さらに、引退のきっかけになったのもこのレースの後でした。
本来なら有馬記念を最後に引退させる計画もあった中、無理な出走スケジュールが続き、屈腱炎という競走馬にとって致命的な故障につながっていきました。
高松宮記念への出走は、ナリタブライアンの晩年を象徴する判断ミスとも言え、その後の病状悪化や早すぎる死とあわせて、「かわいそう」と語られる最大の要因のひとつとなっているのです。
馬主との関係──金か名誉か、決断の裏側
ナリタブライアンの馬主である山路秀則氏とその関係者の行動は、金銭的な目的か、それとも名誉を追い求めた結果かと、たびたび議論の的となってきました。
特に晩年のレース選択やタテガミの処遇をめぐって、ファンからは複雑な感情が寄せられています。
ナリタブライアンが過酷なローテーションを強いられた背景には、馬主と調教師の意向が密接に関わっていたと見られています。
具体的には、ナリタタイシンの菊花賞での無理な出走や、ブライアン自身も故障明けで高松宮記念に出走させられるなど、馬の健康よりも興行的な成果が優先されたかのような例がいくつもあります。
中でも注目されたのが、「とんねるずのハンマープライス」で「ナリタブライアンのたてがみ」が出品された件です。
当初、番組スタッフは本物のたてがみを提供してほしいと依頼しましたが、関係者は「縁起が悪い」として拒否しました。
その後、交渉の末にブラッシングで抜けた毛を提供する形となりました。
この一件が、「金儲けのために馬を傷つけたのではないか」という誤解を生む原因となり、馬主や厩舎側への批判が高まったのです。
さらに、引退後も種牡馬としての活躍が短命に終わったこともあり、現役時代に酷使されたことへの後悔や非難の声が根強く残っています。
結果的に、ナリタブライアンは命を削るようなスケジュールで走らされ、8歳という若さで命を落としました。
こうした背景から、「名誉のために走らせたのか」「金銭的な事情があったのか」といった声が上がるのは自然なことといえるでしょう。
「悔し泣き」の逸話は本当?天皇賞での涙の真相とは
ナリタブライアンが天皇賞で敗れた際に「涙を流した」という逸話は、彼のファンの間で語り継がれる感動的なエピソードです。
この話は事実かどうかの検証を超えて、多くの人の心に深く残っています。
結論から言えば、ナリタブライアンがレース後に涙を流したとされるのは、厳密には医学的に言う「涙」ではなく、目から流れ出た液体が涙のように見えたものとされています。
馬には涙腺はありますが、人間のように感情で涙を流すかどうかは科学的に明確ではありません。
この逸話の舞台となったのは、1996年の春の天皇賞です。
このレースでナリタブライアンはサクラローレルに差されて敗れました。
復帰をかけた重要なレースであったこともあり、競馬ファンの中にはその姿に胸を打たれ、「悔しくて泣いているようだった」と語る人も多くいました。
中には、実況アナウンサーのトーンや、レース後の騎手・南井克巳の表情もあいまって、馬自身が悔しさを感じたのではないかと感じる人も少なくなかったのです。
一部では、目から流れ出た液体は汗や角膜炎によるもの、あるいはレース中の埃などによる刺激で涙腺が反応したとも言われています。とはいえ、これらの情報にかかわらず、「ナリタブライアンが悔し泣きした」という話は、馬にも感情があるという思いを抱かせ、ファンの記憶に刻まれています。
つまりこの逸話は、事実かどうかというよりも、ナリタブライアンという馬がそれだけ多くの人に愛され、感情移入されていた証拠であるともいえるでしょう。
晩年の扱いは適切だったのか?ナリタブライアンの戦績から考察
ナリタブライアンの晩年の扱いは、競馬ファンの間で今も議論の的となっています。
結論から言えば、その戦績や出走内容から見て、適切とは言いがたい部分があると評価されることが多いです。
その理由は、復調が見込めない状態で無理にレースに出走させられたと見える点にあります。
特に股関節炎を発症してからの成績は、三冠馬としての誇りを保てるものではありませんでした。
それでもレースに使われ続けた背景には、関係者の思惑が少なからず影響していたとされています。
具体的には、1995年の阪神大賞典を勝利した直後に股関節炎を発症し、長期休養に入ります。
そして同年秋の天皇賞で復帰するも12着と大敗。
その後もジャパンカップ6着、有馬記念4着と、かつての圧倒的な強さは戻りませんでした。
それにもかかわらず、1996年にはスプリント戦の高松宮記念に出走し、6着という結果で引退を迎えます。
ファンの間では、「宮記念は適正距離ではなかった」「あの時点で引退させるべきだった」といった声が多く聞かれました。
さらに、管理していた大久保調教師や馬主である山路秀則氏に対して、「馬の将来よりも出走回数や話題性を優先したのではないか」という批判も見られました。
名馬にふさわしい終わり方とは何だったのか。
ナリタブライアンの晩年の戦績を追うことで、その扱いが適切だったかを考えるきっかけになります。
タテガミのオークション騒動とは?「かわいそう」と言われる理由
ナリタブライアンが「かわいそう」と語られる理由の一つに、引退後に持ち上がった「タテガミのオークション騒動」があります。
これは、名馬の尊厳や扱いに対する倫理的な問題として、今なお多くの競馬ファンの間で語られている出来事です。
話題の発端は、テレビ番組『とんねるずのハンマープライス』において「ナリタブライアンのたてがみ」が出品されたことでした。
一見すると貴重な記念品のようにも思えますが、これに対し「現役名馬のたてがみを売るのはあまりに酷だ」「金儲けの道具にされた」といった批判が殺到しました。
これが、「かわいそう」と言われる一因となったのです。
しかし、この件には裏話があります。番組側が最初にたてがみのカットを依頼した際、関係者から「競馬界では縁起が悪い」との理由で強く拒否されました。
そこで折衷案として出されたのが、ブラッシング時に自然に抜けた毛の提供でした。
この対応により、直接的に毛を切るという行為は避けられたのです。
とはいえ、「たてがみ」という名目でオークションに出された以上、そのイメージは強く、多くの人に「馬を商品として扱った」という印象を残しました。
この話題は、漫画『馬なり1ハロン劇場』でもネタにされるほど世間の注目を集め、結果としてナリタブライアンが「不当に扱われた存在」として見られる原因のひとつとなりました。
名馬としての誇りを保ったまま引退してほしかったというファン心理が、この騒動に対する「かわいそう」という感情をより強くしたのだと考えられます。
「ナリタブライアンはかわいそう」では済まされない偉大さと影響力
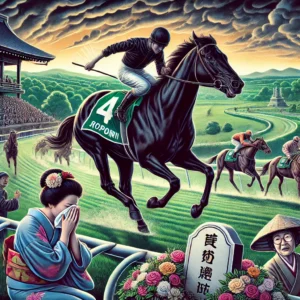
- ナリタブライアンは強すぎる三冠馬──圧巻のパフォーマンスと伝説
- 兄・ビワハヤヒデとの絆と比較──兄弟で歩んだ名馬の宿命
- 子供や産駒たちの現在──ナリタブライアンの血を継ぐものたち
- ライバルたちとの名勝負──クラシックを彩った競走馬たち
- ナリタブライアンはかわいい?ファンが語る見た目と性格
- ゲーム「ウイポ」や記念碑、墓などで語り継がれる伝説の存在
強すぎる三冠馬──圧巻のパフォーマンスと伝説
ナリタブライアンは「強すぎる三冠馬」として語り継がれる名馬です。
その称号にふさわしい走りと実績を残し、今なお競馬ファンの記憶に強く焼きついています。
その理由は、ナリタブライアンが圧倒的な強さを見せた1994年のクラシック三冠達成にあります。
当時の競馬界においても、三冠達成は容易なものではなく、過酷なローテーションをこなしながら、力強く勝ち切ったその姿に「化け物」「異次元」といった評価が集まりました。
具体的には、皐月賞、日本ダービー、菊花賞の三冠全てで完勝を収めたのはもちろん、その内容も他馬を圧倒するものでした。
たとえば日本ダービーでは、2着に7馬身差をつける圧勝。菊花賞では「弟は大丈夫だ!」という実況の名フレーズが生まれたように、絶対的な信頼を寄せられた存在でした。
競馬ファンの間では、「あの頃のナリタブライアンをリアルタイムで見た人にとっては、ディープインパクトも霞む」とまで言われるほど、その影響力は絶大でした。
その後、股関節炎による休養を挟みながらも、復帰戦では勝利を飾り、完全復活への期待が寄せられましたが、残念ながら古馬戦では成績が振るわず、最終的には早すぎる引退と死を迎えます。
しかし、その栄光の三冠は今もなお語り草となっており、「ナリタブライアンは強すぎる」との評価は、決して過剰な賛辞ではないのです。
兄・ビワハヤヒデとの絆と比較──兄弟で歩んだ名馬の宿命
ナリタブライアンとその兄・ビワハヤヒデは、競馬史上でも類を見ない兄弟の名馬として知られています。
両者の歩んだ道は似ていながらも、それぞれに異なるドラマがありました。
この兄弟が注目される理由は、どちらもG1馬としてトップクラスの実力を誇りながら、いずれも怪我によって早期に競走馬としてのキャリアを終えた点にあります。
競馬ファンにとって、この“兄弟で共に頂点に立ちながらも志半ばで去った”という事実は、感動と同時に切なさをもたらしています。
具体的には、ビワハヤヒデは1993年に菊花賞を制し、その翌年には天皇賞(春)や宝塚記念を含むG1・3勝を挙げるなど、古馬王道路線で圧倒的な強さを見せました。
順風満帆に見えたキャリアでしたが、1994年秋に屈腱炎を発症し、引退を余儀なくされます。
一方、弟のナリタブライアンはその年、三冠を達成。
兄の引退と入れ替わるように現れた次なるヒーローとして、競馬界を沸かせました。
このリレーのような活躍は「兄弟の絆」として、多くのファンの胸を打ちました。
しかし、ナリタブライアンもまた故障と戦いながらの晩年を送り、屈腱炎や腸捻転という試練を乗り越えることはできませんでした。
こうして兄弟ともに故障で競走馬としての道を断たれたことから、「この兄弟には宿命のような運命があった」と見る人もいます。
ビワハヤヒデとナリタブライアンは、血統だけでなく競走馬人生の歩みも共鳴する存在でした。
その特別な関係は、今も語り継がれる競馬界の名エピソードとなっています。
子供や産駒たちの現在──ナリタブライアンの血を継ぐものたち
ナリタブライアンの子供や産駒たちは、数こそ限られていますが、その血を受け継いで今も日本の競馬史の中で静かに息づいています。
結論から言えば、産駒として大きな成功を収めた例は少ないものの、その存在はファンの記憶とともに生き続けています。
理由として、ナリタブライアンは種牡馬としての活動期間が非常に短く、後継馬を残す十分な機会に恵まれなかったことがあげられます。引退後まもない1998年、わずか8歳という若さで腸捻転により急死したことで、種牡馬としての道を途中で断たれました。
具体的には、種牡馬として活動した年数はたった2シーズンでした。
その間に残した産駒は数十頭程度とされており、その中には中央競馬で活躍した馬も存在しますが、父を超えるような目覚ましい成績を残すには至りませんでした。
また、牝馬への種付け数も限られていたため、現代にその直系の子孫が競馬場で活躍するケースは稀となっています。
それでも、「ナリタブライアン直系の血統を守りたい」というファンや関係者の想いから、一部の子孫は乗馬や展示馬として、地方の牧場や施設で大切に飼育されている事例もあるようです。
情報が広く公開されていないケースもありますが、「生きた伝説の末裔」として注目を集める存在となっています。
ナリタブライアンの産駒たちは大成することこそ少なかったものの、その血筋は確かに競馬史の一部として今なお語られ続けているのです。
ライバルたちとの名勝負──クラシックを彩った競走馬たち
ナリタブライアンは数々の名馬たちと熱い戦いを繰り広げ、まさにクラシック戦線を代表する存在でした。
その名勝負は今でもファンの間で語り継がれています。
彼が特に注目を浴びた理由は、ただ勝ったからではなく、ライバルたちと織りなすレースの内容がドラマそのものだったからです。
強い馬同士の真剣勝負は、それぞれの個性や背景を際立たせ、競馬の魅力を最大限に引き出しました。
例えば、1994年の皐月賞では、ナリタブライアンが重賞初挑戦の馬たちを相手に1頭だけ次元の違う走りを見せて圧勝し、注目を集めました。
日本ダービーでもその勢いは止まらず、2着馬に7馬身という大差をつけて勝利。
この時の対戦相手の中には、のちにG1戦線で活躍する馬もおり、まさに「ライバルを寄せ付けない強さ」が印象的でした。
また、1996年の天皇賞(春)では、サクラローレルとの接戦が話題になりました。
このレースでブライアンは敗れたものの、「怪我を抱えながらもあそこまで走れた」と、むしろ称賛の声が上がるほどでした。
サクラローレルをはじめ、マヤノトップガンやマーベラスサンデーといった同世代〜近世代の名馬たちとの対決は、時代を象徴する名勝負として知られています。
このように、ナリタブライアンは単なる勝ち馬ではなく、名勝負の中でこそ輝きを放った存在でした。
ライバルとのぶつかり合いこそが、彼の価値をより高め、ファンの心を動かした最大の理由なのです。
ファンが語る見た目と性格
ナリタブライアンは「強すぎる三冠馬」として知られる一方で、「かわいい」と称される一面も持ち合わせていました。
その見た目と性格に、特別な魅力を感じていたファンは多かったのです。
その理由は、無骨で力強い走りとは対照的に、日常の姿には愛嬌があり、親しみやすさがにじみ出ていたからです。
気性が激しいタイプの名馬も多い中で、ナリタブライアンは比較的おとなしく、人懐っこい性格だったと関係者から語られています。
具体的なエピソードとして、調教中の姿や放牧時の様子を間近で見たスタッフの間では、「人に対して心を開いている馬だった」「ブラッシングされると気持ちよさそうにじっとしていた」といった証言があります。
さらに、1990年代に放送されたテレビ番組では、そのたてがみの抜け毛が丁寧に保存されていたことからも、関係者の間で「かわいい存在」として大切にされていた様子がうかがえます。
見た目に関しても、がっしりとした馬体と大きな目が印象的で、「堂々とした風格の中にも優しさを感じた」というファンの声が聞かれました。
実際、漫画『馬なり1ハロン劇場』では「ナリタブライアンの抜け毛」というエピソードがネタとして取り上げられ、その描写でも愛嬌あるキャラクターとして描かれています。
強さと優しさが同居したその存在は、競馬ファンにとって「ただ強いだけの馬」ではなく、「愛されるべきキャラクター」だったのです。ナリタブライアンが「かわいい」と語られるのは、そのギャップと人間味のような魅力に起因しています。
ゲーム「ウイポ」や記念碑、墓などで語り継がれる伝説の存在
ナリタブライアンは、現役を退いた今もなお、多くのファンの記憶に刻まれており、さまざまな形でその伝説は語り継がれています。
結論として、ゲーム・記念碑・墓といった現実とフィクションの両方でその存在が残され、名馬としての影響力は色あせることがありません。
理由として、ナリタブライアンはただのG1馬ではなく、「史上最強」とまで称された三冠馬であったため、その存在は競馬を超えてカルチャー的な価値を持つようになったのです。
とくに1990年代に競馬を見ていた世代にとっては、ナリタブライアンは単なる勝ち馬以上の存在でした。
たとえば、コーエーテクモの競馬育成シミュレーションゲーム『ウイニングポスト(ウイポ)』シリーズでは、ナリタブライアンは必ずと言ってよいほど登場します。
その圧倒的な能力値や、育成のしがいがある馬として、多くのプレイヤーがブライアンを所有し、活躍させることに憧れてきました。
ゲームを通してナリタブライアンの存在を知った若い世代も少なくありません。
現実の世界でも、彼の功績を称える記念碑や碑文が各地に設けられています。
とくに引退後に過ごした牧場では、ファンによる献花やメッセージが今も絶えないとされ、死後の扱いにも愛情が注がれ続けています。墓標やメモリアルプレートを訪ねる「聖地巡礼」のような文化も一部のファンの間で定着しています。
このように、ナリタブライアンは現役時代の実績に加えて、死後の今もゲームや記念碑といった形で人々の心に残り続けています。
それは単なる競走馬ではなく、「伝説」として生き続けている証と言えるでしょう。
総括:ナリタブライアンが「かわいそう」と言われる理由
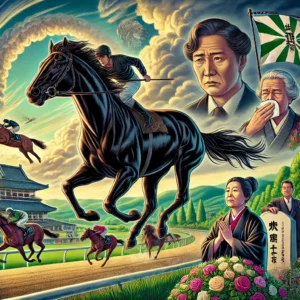
- 屈腱炎に続き腸捻転で急死し、わずか8歳で安楽死処置を受けた
- 高松宮記念で適正外の短距離戦に出走させられたことが疑問視された
- 現役晩年の過密ローテーションが故障と早すぎる死を招いた
- 天皇賞で敗れた際に「悔し泣きした」とされる逸話が切なさを誘った
- 馬主の判断や方針が名誉や金銭目的ではないかと批判された
- タテガミのオークション出品が物議を醸し「商品化された」と批判された
- 種牡馬としての期間が短く、産駒をほとんど残せなかった
- 引退後の扱いや配慮に疑問を持つ声が多く「かわいそう」と語られた
- 強すぎた現役時代との落差が晩年の姿をより悲しく映した
- 天皇賞(春)ではサクラローレルに敗れ、感情を投影するファンも多かった
- 菊花賞後の無理な出走で心身ともに疲弊していったと考えられている
- ブラッシングで抜けた毛をオークションに出品し誤解が広がった
- 兄ビワハヤヒデも故障で引退しており、兄弟そろって早期に表舞台を去った
- 晩年の戦績が振るわず、本来の強さを見せられなかったことが惜しまれる
- 三冠馬の名誉ある引き際としてはふさわしくない最期と受け取られた
- 見た目の可愛らしさと人懐っこい性格が、余計に悲しみを呼んだ
- 競馬ゲームなどで知った若い世代にも「かわいそうな伝説馬」と印象づけられている
- 一部のファンは、牧場などで子孫が大切に飼育されていることに安堵している
- 名レースの数々があるだけに、晩年とのギャップが際立って見える
- 名馬としての誇りを損なうことなく引退させてほしかったという声が根強い

